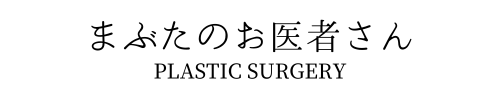こんにちは、金沢です。

平成25年10月6日昭和大学形成外科学教室の同門会学術集会にお招きいただき、旗の台駅から伸びる商店街通りの背景にそびえ立つ高層建築物。昭和大学病院です。
シンポジウム「眼瞼下垂症ー私の工夫ー」
僭越ながら発表させていただきました。
発表内容は形成外科医なら無意識に使っている「とある手技」。
この手技に着目し、応用することで眼瞼下垂症手術時の出血を減らすことができるというもの。抗凝固療法(ワーファリン内服など)や抗血小板療法(バイアスピリン内服など)を受けておられる患者さんも内服を中断せずにマブタの治療を行うことができるようになりました。
出血が少ないと、ダウンタイムも短縮されるし、術者にも余裕が生まれます。
しかし、そんな発表はよそにシンポジウムの議論の主題はもっぱら解剖と手術行程のことばかり。議論は収束することなく、時間が来て終わりました。
まぶたの病態生理については、医師による解釈は、三者三様です。
シンポジウムの座長は鶴切一三先生と岩波正陽先生。
鶴切先生は二重まぶたの形成でシンプルな術式を考案し、今となっては日本に広く普及しており、鶴切法と親しまれております。口調はややぶっきらぼう(ごめんなさい!)ですが、真剣にまぶたのことを追究されており、私自身激励をいただきました。
岩波先生は以前よりまぶたの解剖を研究、発表されており、我々形成外科医にとって貴重な知識を惜しげもなく提供してくださります。medial hornに関する組織解剖の解釈が興味深かったです。
開業の先生達であり、学術的な議論も利害が生じる可能性がある世界では有ります。
しかし、純粋に議論を楽しみ、切磋琢磨する風土があります。
(2015年7月9日 修正)